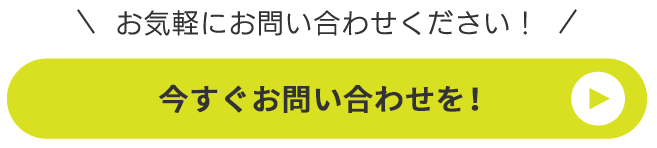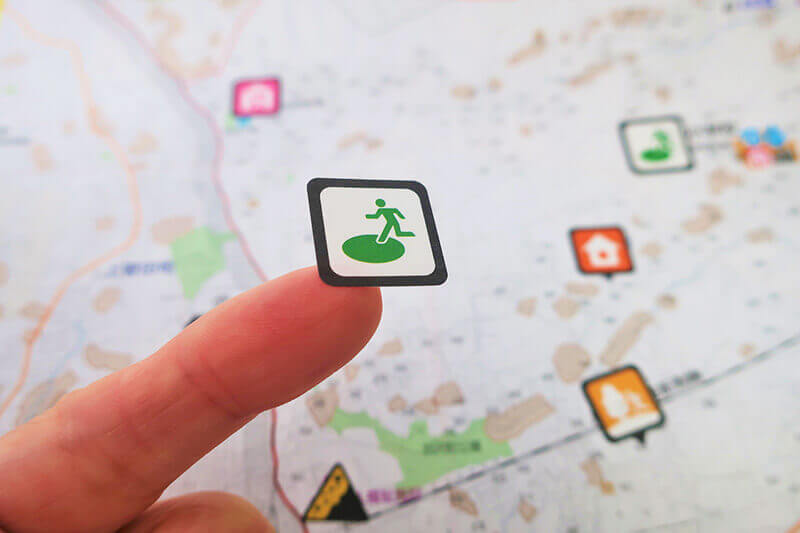
不動産投資において「立地」は収益性を大きく左右する重要な要素ですが、収益だけを見て物件を選ぶと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。その中でも見落とされがちな視点が「災害リスク」です。近年、台風や豪雨、地震、洪水といった自然災害が頻発する中、不動産投資家にとって欠かせないのが「ハザードマップ」を活用したリスク管理です。
本コラムでは、実際の投資家の失敗事例や、リスクを事前に把握し被害を回避した成功事例を交えながら、ハザードマップを使ったリスク管理の重要性について解説していきます。
ハザードマップとは?
ハザードマップとは、国や自治体が提供する、自然災害の被害が想定されるエリアを地図上に可視化したものです。主に以下のような種類があります:
• 洪水ハザードマップ
• 土砂災害ハザードマップ
• 津波ハザードマップ
• 地震動予測地図
• 火山ハザードマップ
これらのマップは、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」や各自治体のホームページから無料で閲覧することができ、誰でもアクセスが可能です。
失敗事例:収益重視で選んだ結果、被災した20代投資家
都内在住のAさん(27歳)は、地方都市に築浅のアパートを購入。利回り9%という好条件に惹かれ、周辺の家賃相場や入居率だけで判断して購入を決断しました。しかし、購入からわずか半年後、集中豪雨により物件周辺が浸水。建物の1階部分が被害を受け、1階の2部屋が長期にわたり空室となってしまいました。
調査してみると、そのエリアは洪水ハザードマップで「浸水深さ最大3.0m」と明記された地域だったのです。火災保険の水災補償にも未加入だったため、多額の修繕費用が自己負担に。結果、キャッシュフローは大幅に悪化し、物件売却も視野に入れざるを得なくなったといいます。
成功事例:ハザードマップで回避した女性投資家
一方、Bさん(34歳・女性)は、神奈川県内の中古戸建を購入検討していました。物件はリフォーム済みで利回りも高く、内見時の印象も非常に良好。しかし、購入前にハザードマップを確認したところ、土砂災害警戒区域に該当していることが判明。
さらに、市役所で過去の災害履歴を調査した結果、10年前に裏山が崩れ、隣接住宅に被害が出たことを知ります。Bさんは物件購入を見送り、代わりに同等の利回りでリスクの低い平地の物件を購入。現在も満室稼働中で、安定した家賃収入を得ています。
不動産投資でのハザードマップ活用方法
1. 購入前の立地調査に活用
物件の立地がどのような災害リスクにさらされているのかを、まず把握することが大切です。たとえば、洪水リスクがあるかどうか、水位の想定深さ、避難所までの距離、土砂災害警戒区域の有無などを調べることができます。
2. 保険選定の参考にする
エリアの災害リスクを把握したうえで、火災保険・地震保険の補償内容を見直すことも重要です。たとえば洪水リスクが高い地域では、水災補償は必須といえるでしょう。
3. 物件価値の維持に役立てる
災害リスクが高い地域では、売却時にも買い手が慎重になります。将来的な資産価値の維持という観点でも、リスクの少ないエリアを選ぶことで、出口戦略がスムーズに進みます。
リスクを避けるだけでなく、価値を見出す視点も
ハザードマップでリスクを把握することは、単に「危ない地域を避ける」ためだけではありません。たとえば、洪水リスクが高い地域であっても、そのリスクに見合った価格で取得し、耐水リフォームや保険を徹底することで、割安に仕入れて収益を上げる戦略もあります。
また、再開発によって災害対策が進んでいるエリアもあるため、過去のリスク情報と現在の整備状況を照らし合わせることも、プロの視点として重要です。
まとめ:災害リスクも投資判断に組み込む時代へ
近年の自然災害の多発により、不動産投資においては「災害リスク=投資リスク」という認識が定着しつつあります。高利回りや好立地という表面的な条件だけで判断せず、ハザードマップを活用して立地の安全性を見極めることは、長期安定経営の大前提といえるでしょう。
「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、ハザードマップを使ったリスク管理を“投資の基本”として身につけることが、今後の不動産投資家の必須スキルとなります。
不動産投資のリスク管理に不安がある方は、当社カスタマーサービスまでお気軽にご相談ください。個別の立地リスク分析や、災害リスクに備えた運用プランのご提案も承っております。
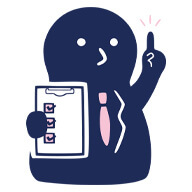
不動産業界に25年以上在籍。多くの不動産投資の問題を解決してきた、猫と温泉をこよなく愛する東京在住47歳。