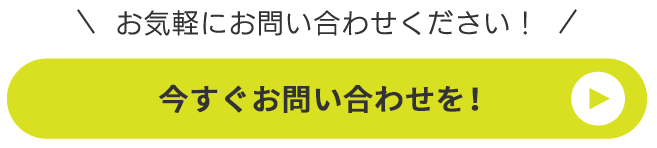~リスクを回避して長期安定収益を実現するために~

不動産投資において「利回り」や「築年数」「立地の利便性」などを重視するのは当然のことです。しかし、それらと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「地価の動向」です。
特に「今後、地価が下がるエリア」をいかに見抜き、リスクを避けるかは、長期にわたる不動産経営において極めて大切な視点となります。
本コラムでは、地価が下がるエリアに共通する兆候や、失敗事例・成功事例を交えて、不動産投資家が押さえておくべき「地価下落リスクの見抜き方」を詳しく解説します。
地価が下がるエリアの典型的な兆候とは?
1. 人口が減少している地域
地価に最も大きな影響を与えるのが「人口動態」です。住民が減少している地域では、住宅需要も減少し、賃貸物件の空室リスクが高まります。結果として物件の価値が下がり、地価も下落します。
チェックポイント:
• 国勢調査の人口推移
• 市区町村が発表する人口ビジョン
• 年齢別人口構成(高齢化率が高いほど要注意)
2. 空き家が増えている地域
街を歩いてみて「シャッターが閉まった店舗が多い」「売地や空き家が点在している」と感じたら注意が必要です。供給過多のサインともいえ、賃貸ニーズが減少傾向にある証拠です。
データ活用:
• 総務省「住宅・土地統計調査」の空き家率
• 地元不動産業者のヒアリング
3. 大規模施設の撤退や雇用減少
その地域の経済を支えていた大企業や工場、大学、病院などの主要施設が撤退または縮小した場合、住民の流出につながります。特に「単一産業に依存している地方都市」は、こうした影響を受けやすい傾向にあります。
確認方法:
• 地域ニュースや市役所の広報
• 雇用統計の動向
• ハローワーク求人件数の推移
【失敗事例】「駅近・高利回り」に飛びついたが…
東京近郊在住のCさん(30代・会社員)は、地方都市の駅徒歩8分・築浅の1Rマンションを「表面利回り10%」に惹かれて購入しました。当初は満室経営が続いたものの、3年後に近隣の大学がキャンパスを縮小し、学生数が激減。そこから退去が相次ぎ、以降の入居付けに苦戦し、家賃も10%以上ダウン。
調べてみると、物件エリアは過去5年間で人口が1割以上減っており、駅前の商業施設も次々と閉鎖されていました。地価も毎年下落傾向にあり、「出口戦略」が難航することが見込まれています。
【成功事例】再開発エリアを見極めた堅実投資
一方、Dさん(40代・公務員)は、東京23区外の「一見地味な駅前エリア」に着目。地価は横ばいだったものの、数年後に市による再開発事業が予定されており、道路拡張や商業施設の誘致が進む計画がありました。
現地調査や市の都市計画資料を元に、駅徒歩10分の築古アパートを安価に取得。2年後には地価が上昇し、近隣に新築マンションが次々建設され、賃料も上昇。資産価値が向上し、今では銀行からの追加融資にもつながっています。
地価下落リスクを避けるためのチェックリスト
不動産投資で「地価が下がるエリア」を見抜くために、以下のポイントを事前にチェックしましょう:
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口推移 | 市区町村単位での人口増減を5年以上で確認 |
| 空き家率 | エリア全体の空き家の増減傾向 |
| 雇用環境 | 主要産業・雇用主の動向、求人数の推移 |
| 都市計画 | 市の再開発計画、用途地域の見直し予定など |
| インフラ整備 | 鉄道延伸、道路開発、公共施設の新設情報 |
| 教育機関 | 大学・高校などのキャンパス統廃合の予定 |
| 災害リスク | ハザードマップでの洪水・地震リスクも併せて確認 |
「安い物件」ではなく「価値の下がらない物件」を選ぶ
不動産投資では「安い物件=お得」と考えがちですが、それが「地価下落の初期サイン」である可能性もあります。投資額を抑えることは重要ですが、それ以上に「将来にわたって価値が下がりにくい立地を選ぶ」ことが成功への近道です。
地価が安定しているエリア、今後の開発余地があるエリア、公共交通機関の整備が進むエリアなど、時間と手間をかけて調査した上で選定することが、安定収益と資産価値維持につながる鍵となります。
まとめ:未来を見据えた「逆算型投資」が鍵
地価は一朝一夕に変化するものではありませんが、「下がる兆候」は早くから現れています。大切なのは「今が良い」ではなく「今後どうなるか」という未来視点で判断すること。
地価が下がるエリアには共通する特徴があります。それを事前に見抜き、回避することができれば、不動産投資のリスクを大きく下げることができます。
当社カスタマーサービスでは、投資候補地のリスク調査や地価動向分析も無料でサポートしています。初めての方でも安心してご相談いただけます。
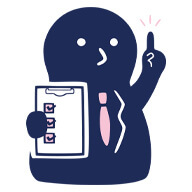
不動産業界に25年以上在籍。多くの不動産投資の問題を解決してきた、猫と温泉をこよなく愛する東京在住47歳。