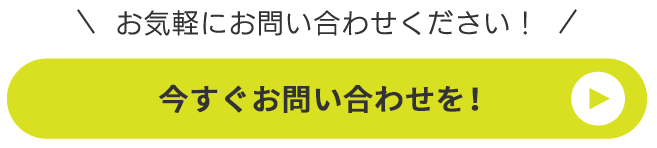不動産投資において、「管理会社に任せておけば安心」と思っていませんか?
確かに、日常的なクレーム対応や家賃の集金、入居者募集といった実務はプロに委託することで手間が省けます。
しかし、「すべてを任せきり」にしてしまうと、知らぬ間に損失やトラブルが発生しているケースも少なくありません。本コラムでは、実際に相談窓口で寄せられた管理会社とのトラブル事例をもとに、気をつけるべきポイントと予防策をご紹介します。
よくあるトラブル事例1:空室放置と対応の遅れ
《事例》:神奈川県のアパートオーナー(60代)
管理会社に任せて1年が経過しても、1室がずっと空室のまま。「なぜ埋まらないのか」と理由を聞いても、「時期が悪い」「様子を見ましょう」と曖昧な回答。後から調査すると、募集広告がポータルサイトに未掲載だったことが判明。
原因と背景
管理会社の中には「空室対応が後回し」「手間のかかる広告出稿を怠る」といったケースがあります。特に複数物件を抱える大手では、オーナーとのコミュニケーション不足から優先度が下がることも。
対策
• 募集状況を月1で報告させるルールを設定
• 自身でもSUUMOやホームズで掲載を確認
• 管理契約に「募集活動の定期報告義務」を明記する
よくあるトラブル事例2:家賃滞納の放置
《事例》:埼玉県の区分マンションオーナー(40代)
家賃の入金が数ヶ月間ないことに気づき、管理会社に問い合わせたところ「滞納が続いているが、強く督促はしていない」との回答。結局6ヶ月以上未納となり、訴訟にまで発展。
原因と背景
督促業務に消極的な管理会社や、入居者との関係悪化を恐れて対応が曖昧になるケースがあります。また、家賃保証会社が未加入だと、損失が直撃します。
対策
• 家賃保証会社の導入を必須条件に
• 滞納発生時のフロー(何日後に督促、何日後に通告等)を契約書に明記
• 月次報告に入金ステータスを必ず含めるよう依頼
よくあるトラブル事例3:修繕費用の水増し・勝手な発注
《事例》:大阪市のRC物件オーナー(50代)
共用部の電球交換や壁補修などで、毎月数万円の修繕費が発生。明細を見ると「高額な工事費」「業者の選定理由不明」が目立ち、オーナーの承認なしに修繕を発注していたことが後から判明。
原因と背景
管理会社と提携する業者に丸投げしており、利益を上乗せしていた可能性も。業者の見積もり精査や相見積もりが行われていないケースが多いです。
対策
• 2万円以上の修繕は事前承認必須とする契約条項を加える
• 見積書の提示と、相見積もりの徹底を要求
• オーナー主導で業者を選定することも視野に
よくあるトラブル事例4:入居者トラブルの放置
《事例》:福岡市のアパートオーナー(30代)
入居者間で騒音・ゴミ出しのトラブルが頻発。クレームを管理会社に伝えても「対応しています」と言うばかりで、具体的な行動が見えず放置状態結局、良質な入居者が先に退去する事態に。
原因と背景
管理会社の「事なかれ主義」によって、トラブル対応が曖昧になり、建物全体の評判悪化や退去リスクにつながるケースがあります。
対策
• トラブル発生時の初動対応フローを管理会社と共有
• 近隣住民の声や管理日報など、証拠を残して報告を求める
• 必要なら定期巡回・臨時訪問を依頼
トラブルを未然に防ぐために必要なこと
任せっきりの姿勢では、オーナー自身が損失を被るリスクが高まります。以下の点を意識することで、トラブルの芽を摘むことができます。
管理契約の内容を見直す
「報告義務」「承認事項」「費用上限」など、曖昧な点は明文化し、双方の認識を揃えることが重要です。
定期的なコミュニケーション
最低でも月1回は報告・打ち合わせの機会を設け、信頼関係を築くことで、怠慢な対応を防ぐことができます。
管理会社の変更も視野に
改善が見られない場合は、思い切って管理会社を変更することも選択肢の一つです。複数社で相見積もりを取ることで、より良いパートナーと出会える可能性があります。
まとめ:任せる≠無関心。オーナーの主体性が資産価値を守る
不動産投資は「管理が9割」と言われるほど、物件の収益性は日常の運用で大きく左右されます。信頼できる管理会社とともに、オーナー自身も積極的に関わる姿勢が、トラブル回避と安定経営の鍵です。
「任せる」と「丸投げ」は違います。
資産を守るのは、他の誰でもない、オーナー自身の行動です。
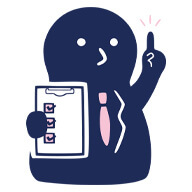
不動産業界に25年以上在籍。多くの不動産投資の問題を解決してきた、猫と温泉をこよなく愛する東京在住47歳。