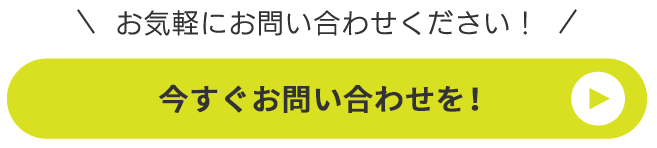「家賃保証付きだから安心」と思って契約したサブリース。しかし、数年後に突然通知が届き、「保証家賃を下げます」「契約を打ち切ります」—。このようなトラブルが近年、全国的に増えています。
実際に相談窓口には「話が違う」「泣き寝入りするしかないのか?」という声が多数寄せられています。
本コラムでは、実際の相談内容をもとに、サブリース契約で家賃保証が打ち切られた背景と、そこにどんな回避策があったのかを掘り下げます。これから不動産投資を始める方、すでにサブリース契約をしている方はぜひ参考にしてください。
相談事例:新築アパートを一括借上げ契約、5年後に家賃保証が消えた
相談者プロフィール
• 年齢:40代後半
• 職業:会社員
• 購入物件:地方都市の新築アパート(1棟8室)
• 契約内容:家賃保証付きのサブリース契約(保証期間:2年、以後更新制)
契約当初は満室を維持し、家賃も毎月安定。営業担当から「20年間は安定収入が入る」との説明もあり、安心していたそうです。
しかし、5年目の更新時にサブリース会社から届いたのは、「来期から家賃保証額を30%減額する」という通知。
納得できずに抗議したものの、「契約書に“保証家賃の見直しを行うことがある”と明記してある」と言われ、泣く泣く減額に応じたとのことでした。
なぜ家賃保証が打ち切られたのか?
ここで重要なのは、「サブリース契約」は借主との間で交わす「転貸契約」であるという点です。
サブリース契約の主な特徴
• 契約期間の中途でも賃料の改定が可能な条項が入っていることが多い
• 貸主(オーナー)にとって不利な内容でも、有効と判断されるケースがある
• 賃借人(入居者)との契約ではないため、強い保護が受けられない
国民生活センターなどにも「思っていた内容と違う」とする相談が数多く寄せられており、2020年からは不動産業者に対して重要事項説明の義務化が強化されるに至っています。
回避策は本当にあったのか?
それでは、家賃保証の打ち切りや減額を避けるために、事前にできたことは何だったのでしょうか?ここでは4つの視点から解説します。
① 契約書を事前に第三者に見てもらう
営業トークに安心せず、契約書を専門家(不動産の法律相談、宅建士、行政書士など)に見せることが重要です。
「保証額は◯年間固定」「減額にはオーナーの同意が必要」などの条項があるかを確認しましょう。
② 賃貸需要のあるエリアか調査する
そもそもサブリースが必要なエリア=空室リスクが高いエリアという可能性もあります。
自分でエリア分析をし、サブリースに頼らなくてもやっていける地域かどうかを見極めるべきでした。
③ 複数社で見積もり・契約比較を行う
1社に絞って契約してしまう前に、複数の管理会社・サブリース会社と条件比較を行うことも大きな予防策になります。
競合比較をすれば、法外な手数料や極端に不利な契約条件に気づけるはずです。
④ フルローン前提での収支計画を見直す
家賃保証が下がった場合のシミュレーションをしていなかった点も大きな盲点でした。
家賃が20〜30%下がった場合でもキャッシュフローが赤字にならないか、事前に複数パターンのシミュレーションを行うことが大切です。
サブリースが悪いわけではない。大事なのは「理解と準備」
サブリース=悪徳、というわけではありません。
実際、築古物件や郊外物件で空室リスクが高い場合、一定の収入を安定させる手段としてサブリースが有効なケースもあります。
ただし、「任せきり」「説明を信じすぎる」ことで発生するリスクが非常に大きいのが現実です。
今回のように「保証があるから安心」と思っても、契約書には必ず**“見直し可能”の逃げ道**が用意されているケースが多いのです。
まとめ:不動産投資は「契約がすべて」
今回の事例のように、“最初の確認不足”が数年後の損失に直結するのが不動産投資の怖いところです。
サブリース契約は、きちんと仕組みを理解していれば有効に使える制度でもあります。
しかし、不安要素や疑問点がある場合は、契約前に必ず相談窓口や第三者の専門家に意見を求めましょう。
「こんなはずじゃなかった」をなくすために、最初の1歩を慎重に。
あなたの不動産投資が成功につながるよう、今後も実例に基づいたコラムをお届けしていきます。
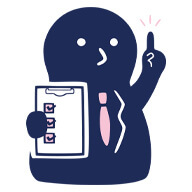
不動産業界に25年以上在籍。多くの不動産投資の問題を解決してきた、猫と温泉をこよなく愛する東京在住47歳。